
2018年3月27・29日開催 編集委員会主催 Fisheries Science 論文投稿セミナー
「学会のオフィシャル国際誌としてFSが目指すところ」資料集
| 開催記録 | 日本水産学会誌 2018; 84(4): 掲載準備中 |
| スライド・資料 | 編集委員会講演スライド (PDF 1.8 MB) より円滑な投稿審査のために |
| Slides of Editorial Board's presentation (PDF 1.2 MB) Important Things in Paper Submission | |
| シュプリンガー講演スライド (PDF 1.3 MB) Publishing Your Research--Tips & Tricks |
Fisheries Science 論文投稿セミナー 編集委員会委員長 潮 秀樹
記
「学会のオフィシャル国際誌としてFSが目指すところ」の開催について
| 主 催 | 編集委員会 |
| 日 時 | 平成30年3月27日(火)・29日(木)12:00-13:00 |
| 場 所 | 東京海洋大学品川キャンパス (〒108-8477 東京都港区港南4-5-7) |
| 企画責任者 | 潮 秀樹(東大院農)・片山知史(東北大院農)・舞田正志・廣野育生(海洋大)・木下政人(京大院農)・井上広滋(東大大気海洋研) |
| 参 加 費 | 無料(先着80名まで軽昼食の用意あり) |
| 申 込 | 不要 |
| 趣 旨 | 水産業界においても国際競争が激化する中,水産学研究の発信力への期待は高まっている。日本水産学会のオフィシャルジャーナルである英文誌 Fisheries Science (通称FS)も,国内外の優れた研究を発表し,社会における課題や問題点を議論する場として,信頼のおけるピアレビューの伝統を守りつつ,研究者の研究業績や社会貢献に焦点を当てる発信力のある雑誌となるべく,転換の時期に直面している。本セミナーでは,正会員,学生会員を問わず知っておいてほしいテーマとして,出版社(シュプリンガー・ネイチャー)と編集委員会のジャーナル出版事業に対する展望と,研究者が戦略的に論文公表を進める際に必要な,投稿の手順,原稿作成や審査の視点,国際標準として注意の必要な事項などを解説する。本セミナーは日英2言語で1回ずつ開催する(27日は日本語,29日は英語)。 |
| プログラム | |
| 12:00-12:05 | 開会挨拶・趣旨説明 |
| 12:05-12:20 | 論文投稿に関する国際標準の概念 (シュプリンガー・ネイチャー) |
| 12:20-12:40 | 国際発信力と学会誌としてのFSの今後の方向性 (編集委員会) |
| 12:40-12:55 | 質疑応答 |
| 12:55 | 閉会挨拶 |
| 問い合わせ先 | 公益社団法人日本水産学会事務局(編集担当 寺島) Tel : 03-3471-2165 Email : fsjpubl@d1.dion.ne.jp 学会ホームページにおいても随時情報を掲載します。 |
以上
| ・日本語版 | FS_Ref-S-Ins_J_20170919.docx |
| ・英 語 版 | FS_Ref-S-Ins_E_20170919.docx |
また,すでに受付を済ませて審査を受けている投稿については,査読完了などの区切りのついた段階で編集委員より改めてご案内申し上げますので,その際に原稿をご修正下さい。
なお,和文誌の『日本水産学会誌』は従来通りの番号制を続けますので,お間違いのないようご注意下さい。
その他ご不明の点がありましたら,日本水産学会事務局までお問い合わせ下さい。
公益社団法人日本水産学会 事務局
Email: fsjpubl@d1.dion.ne.jp(編集)
Tel: (03)3471-2165 Fax: (03)3471-2054
編集委員会委員長 佐藤秀一Fisheries Science 83巻表紙写真などの募集について
このたび,来年の83巻の表紙に掲載する写真・図を日本水産学会会員の皆様から募集いたします。写真は漁業,養殖,水産生物,水産食品など水産学会が扱う範疇であれば特に制限するものではありませんが,一枚の写真でインパクトのある内容を表現できることが要求されます。掲載が決定した方には,Fisheries Science 83巻を6冊(1〜6号各1冊)進呈致しますので,奮ってご応募ください。過去に発行されましたFisheries Scienceの表紙デザインは,学会ホームページ http://www.office.jsfs.jp/fs-cover2.htmlでご覧いただけます。
| ◆FS誌表紙写真募集要項 | |
| テーマ: | 日本水産学会が取り扱う分野に関連した,表紙にふさわしい写真または図版 |
| 作品の種類: | 未公表の写真または図版 *作品中に他人が著作権等を持つ著作物等が含まれる場合には,応募者の責任において,その著作権者等から応募のための複製の許可を得てください。また,人の肖像等を利用する場合についても同様とします。 |
| 応募締切: | 平成28年7月1日(消印有効) |
| 応募資格: | 日本水産学会会員であること |
| 応募作品の規格等: | ・解像度300 dpi以上のTIFF, EPS, JPEGのいずれかの形式で保存したファイル ・印刷サイズ(縦5 cm × 横7 cm程度)に縮小した際に,識別可能であること |
| 応募方法: |
下記まで,電子メール添付,またはCD等のディスクにコピーしたものを郵送してください。 公益社団法人日本水産学会 〒108-8477 東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学内 Email: fsjpubl@d1.dion.ne.jp ・郵送での応募は,応募締切日の消印有効とします。 ・応募作品には,内容がわかる簡単な説明文(日本語および英語)を付け,応募者の氏名と所属,連絡先住所を明記してください。 ・なお,作品中に他人が著作権を持つ著作物等が含まれる場合には,許諾を得た著作物等とその著作権者等の連絡先のリストを応募資料として添付してください。 |
| 応募作品の返却: | 応募作品は返却しません。 |
| 採用作品の選考: | 応募作品は日本水産学会編集委員会が審査し,採用作品6点以内を選定します。 |
| 採用作品の発表: | 採用作品については2016年8月15日までに本人に結果を電子メールで通知するとともに,著作物利用許諾契約書を郵送します。 |
| 採用作品の著作権: | 採用作品の著作権は応募者に帰属します。 ただし採用作品の応募者には, (1) 学会誌冊子およびパンフレット,ポスター,等の宣伝物,CDもしくは類似の電子媒体のラベルなどの印刷物における利用 (2) 学会および出版社のホームページ,論文データベース等,Fisheries Science誌に関するインターネットサイトにおける利用 (3) 学会の活動報告資料における利用 について,学会が採用作品を独占的に利用することを了承していただきます。 採用作品の利用期間は,2017年12月末日までとしますが,それまでに製作した表紙デザインの複製物および翻案は,継続的に学会が利用できることとします。 以上の範囲以外で学会が採用作品を利用する場合は,事前に応募者との間でその条件について協議するものとします。 |
編集委員会委員長 佐藤秀一
Fisheriessciences.com誌は,トルコの水産関係の科学者を中心にEditorial Boardを組み,いわゆるゴールドオープンアクセスと呼ばれる,著者がオープンアクセス料金を負担して論文をオープンアクセス公開しているジャーナルです。(対して,Fisheries Science誌のオープンアクセス公開は著者が料金を負担することに変わりはありませんが,あくまでオプションサービスであり,ジャーナル自体は論文掲載料と購読料の課金を主体財源とした出版形態を取っています。)編集委員会がFisheriessciences.com誌のEditor-in-ChiefであるDr. Ozkan Ozdenに連絡したところ, Fisheriessciences.com誌の編集においてはEditorがリジェクトしたはずの論文が掲載されるなど,トラブルが何度かあったので,iMedPub社にはすでに辞意を表明しているが,いまだにEditor-in-Chiefとして名前が使われているとの回答がありました。
編集委員会委員長 佐藤秀一
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/suisan/advpub/0/_contents/-char/ja/
J-STAGEの日本水産学会誌トップページからアクセスする場合は,画面左側の【最新巻号】欄に表示の【早期公開】をクリックして下さい。
(日本水産学会誌80巻3号会告)
編集委員会委員長 東海 正
Fisheries Science誌に類似したタイトルの雑誌からの
投稿勧誘に対する注意
近年,オンラインジャーナルやオープンアクセスジャーナル出版の増加に伴い,既存のジャーナルや国際会議等を騙った,あるいは類似の名称で,投稿や編集,会議参加を促すなどのメールによるフィッシング行為や詐欺,実体もしくは実績のない出版社の営業活動によるトラブルが増えていることは,日本水産学会誌81巻4号掲載の会告でもお知らせした通りですが,一昨年よりFisheriessciences.comというオンラインジャーナルからの投稿勧誘メールが会員へ回っており,Fisheries Science誌と名称が紛らわしいので学会として対策を取るように会員から苦情をいただいております。
編集委員会はSpringer社とともに,Fisheriessciences.com誌を出版しているiMedical Publishing (iMedPub)社に対して書面において警告し,対応を求めてきましたが,改善が見られません。最近では,Fisheries Science誌が投稿システムとして採用しているEditorial Managerを利用しての投稿受付も始めたようで,学会としてはFisheries Science誌と混同して,会員が不利益を被ることがないか危惧するところであります。
Fisheries Science誌とFisheriessciences.com誌の投稿受付サイトのログイン画面は,以下のように違いますので,ご留意下さい。
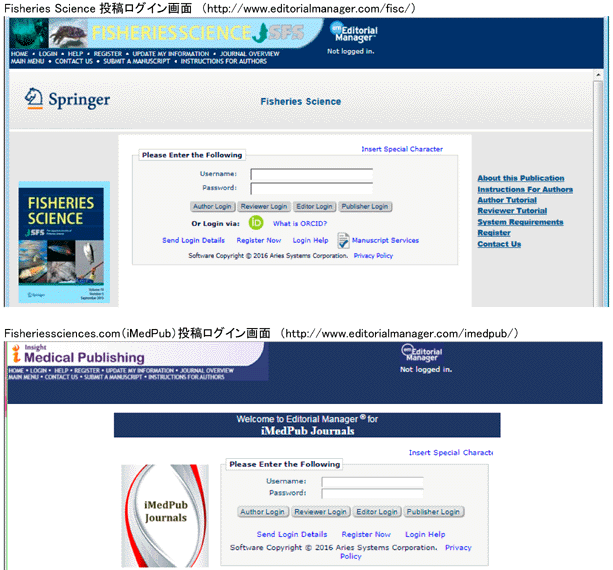
また,Thomson Reutersのロゴが勧誘メールやジャーナルのホームページに表示されていますが,このジャーナルは動物学分野のあらゆるジャーナルが登録されているZoological Recordに登録されているだけであり,Impact Factorの集計に用いられているScience Citation IndexやScience Citation Index Expandedなどのデータベースには登録されていないことも調査済みです。
編集委員会としては,引き続きiMedPub社へ,Fisheries Science誌と混同しやすい勧誘および宣伝行為は行わないよう,要求していくつもりです。
つきましては,会員の皆様におかれましてはFisheriessciences.com誌に限らず,論文投稿や編集活動への勧誘を受けた際には,ジャーナルを発行している学協会もしくは出版社のバックグラウンド,ジャーナルの実績,金銭トラブル発生の可能性のないことなどをご確認の上,慎重にご対応下さいますようお願い申し上げます。トラブルの多いオープンアクセスジャーナルを出版している会社を紹介しているBeall's List (http://scholarlyoa.com/publishers/)なども参考になります。
日本水産学会が出版している学会誌(日本水産学会誌,Fisheries Science誌)については,メールによって広く一般に投稿の勧誘をすることはありません。また,査読依頼やエディター就任依頼も,関連分野の編集委員もしくは学会事務局(fsjpubl@d1.dion.ne.jp)よりご連絡を差し上げておりますので,お心当たりのないメールアドレスからの連絡については,直接返信されないようお薦めします。
オープンアクセス出版も,現在のところは著者からの受注によって適用するシステムになっておりますので,編集委員会から依頼状を送付して執筆を依頼する場合でない限りは,投稿前からオープンアクセス出版を確約することはございません。日本水産学会誌の報文オンライン版の早期公開開始
日本水産学会誌の冊子版発行に先立ち,受理報文(論文,短報,総説)を,オンラインでいちはやく閲覧することができるようになりました。
早期公開版では,掲載号とページ数は確定していませんが,公式出版物の扱いになりますので,doi番号を使って引用することも可能です。
ぜひ最新情報としてご活用下さい。Fisheries Science 81巻表紙写真などの募集について
このたび,来年の81巻の表紙に掲載する写真・図を日本水産学会会員の皆様から募集いたします。写真は漁業,養殖,水産生物,水産食品など水産学会が扱う範疇であれば特に制限するものではあませんが,一枚の写真でインパクトのある内容を表現できることが要求されます。掲載が決定した方には,Fisheries Science 81巻を6冊(1〜6号各1冊)進呈致しますので,奮ってご応募ください。過去に発行されましたFisheries Scienceの表紙デザインは,学会ホームページ http://www.office.jsfs.jp/fs-cover2.htmlでご覧いただけます。
| ◆FS誌表紙写真募集要項 |
| テーマ: | 日本水産学会が取り扱う分野に関連した,表紙にふさわしい写真または図版 |
| 作品の種類: | 未公表の写真または図版 *作品中に他人が著作権等を持つ著作物等が含まれる場合には,応募者の責任において,その著作権者等から応募のための複製の許可を得てください。 また,人の肖像等を利用する場合についても同様とします。 |
| 応募資格: | 日本水産学会会員であること |
| 応募作品の規格等: | ・解像度300 dpi以上のTIFF, EPS, JPEGのいずれかの形式で保存したファイル ・印刷サイズ(縦5 cm × 横7 cm程度)に縮小した際に,識別可能であること |
| 応募締切: | 平成26年7月1日(消印有効) |
| 応募方法: |
上記期間内に下記まで,電子メール添付,またはCD等のディスクにコピーしたものを郵送してください。 公益社団法人日本水産学会 〒108-8477 東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学内 Email: fsjpubl@d1.dion.ne.jp(@dの次は数字の1) ・郵送での応募は,応募締切日の消印有効とします。 ・応募作品には,内容がわかる簡単な説明文(日本語および英語)を付け,応募者の氏名と所属,連絡先住所を明記してください。 ・なお,作品中に他人が著作権を持つ著作物等が含まれる場合には,許諾を得た著作物等とその著作権者等の連絡先のリストを応募資料として添付してください。 |
| 応募作品の返却: | 応募作品は返却しません。 |
| 採用作品の選考: | 応募作品は日本水産学会編集委員会が審査し,採用作品6点以内を選定します。 |
| 採用作品の発表: | 採用作品については平成26年8月15日までに本人に結果を電子メールで通知するとともに,著作物利用許諾契約書を郵送します。 |
| 採用作品の著作権: |
採用作品の著作権は応募者に帰属します。 ただし採用作品の応募者には, (1) 学会誌冊子およびパンフレット,ポスター,等の宣伝物,CDもしくは類似の電子媒体のラベルなどの印刷物における利用 (2) 学会および出版社のホームページ,論文データベース等,Fisheries Science誌に関するインターネットサイトにおける利用 (3) 学会の活動報告資料における利用 について,学会が採用作品を独占的に利用することを了承していただきます。 採用作品の利用期間は,採用作品が表紙として使われる平成27年12月末日までとしますが,それまでに製作した表紙デザインの複製物および翻案は,継続的に学会が利用できることとします。 以上の範囲以外で学会が採用作品を利用する場合は,事前に応募者との間でその条件について協議するものとします。 |
(日本水産学会誌80巻3号会告)
編集委員会委員長 東海 正J-STAGEにおける日本水産学会誌の全面オープンアクセス化について
本会にとって日本水産学会誌の刊行は公益目的事業のひとつの大きな柱であり,水産学研究の成果を広く普及するためにも,全面的にオープンアクセスとすることとしました。これにより,J-STAGEのJournal@rchive と合わせて,日本水産学会誌が創刊号から全巻を通して会員,非会員を問わずインターネット上で自由にご覧頂くことができます。
また,本会ホームページ http://www.jsfs.jp/ では,東日本大震災に関するお知らせのページを設けて,本会の復興支援の活動を報告するとともに,日本水産学会誌上の復興の足がかりとなる連載記事や放射能関係の文献リストから記事本文をご覧いただけるようにしております。これを機に,本会に集められた学術情報を幅広くご活用いただき,社会に役立てていただければと考えます。
編集委員会委員長 東海 正Fisheries Science 80巻表紙写真などの募集について
このたび,来年の80巻の表紙に掲載する写真・図を日本水産学会会員の皆様から募集いたします。写真は漁業,養殖,水産生物,水産食品など水産学会が扱う範疇であれば特に制限するものではありませんが,一枚の写真でインパクトのある内容を表現できることが要求されます。掲載が決定した方には,Fisheries Science 80巻を6冊(1〜6号各1冊)進呈致しますので,奮ってご応募ください。過去に発行されましたFisheries Scienceの表紙デザインは,学会ホームページ http://www.office.jsfs.jp/fs-cover2.htmlでご覧いただけます。
| ◆FS誌表紙写真募集要項 |
| テーマ: | 日本水産学会が取り扱う分野に関連した,表紙写真にふさわしい写真または図版 |
| 作品の種類: | 写真または図版 |
| 作品は未公表のものとします。なお,作品中に他人が著作権等を持つ著作物等が含まれる場合には,応募者の責任において,その著作権者等から応募のための複製の許可を得てください。また,人の肖像等を利用する場合についても同様とします。 |
| 応募資格: | 日本水産学会会員であること |
| 応募作品の規格等: | 解像度300 dpi以上のTIFF, EPS, JPEGのいずれかの形式で保存したファイル。印刷サイズ(縦5 cm × 横7 cm程度)に縮小した際に,識別可能であること。 |
| 応募締切: | 平成25年7月10日 |
| 応募方法: | 上記期間内に学会事務局まで,電子メール添付,またはCD等のディスクにコピーしたものを郵送してください。 公益社団法人日本水産学会 〒108-8477 東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学内 Email: fsjpubl@d1.dion.ne.jp(@dの次は数字の1) |
| ・ | 郵送での応募は,応募締切日の消印有効とします。 |
| ・ | 応募作品には,内容がわかる簡単な説明文(日本語および英語)を付け,応募者の氏名と所属,連絡先住所を明記してください。 |
| ・ | なお,作品中に他人が著作権を持つ著作物等が含まれる場合には,許諾を得た著作物等とその著作権者等の連絡先のリストを応募資料として添付してください。 |
| 応募作品の返却: | 応募作品は返却しません。 |
| 採用作品の選考: | 応募作品は日本水産学会編集委員会が審査し,採用作品6点以内を選定します。 |
| 採用作品の発表: | 採用作品については平成25年8月15日までに本人に結果を電子メールで通知するとともに,著作物利用許諾契約書を郵送します。 |
| 採用作品の著作権: | 採用作品の著作権は応募者に帰属します。ただし採用作品の応募者には,(1) 学会誌冊子およびパンフレット,ポスター,等の宣伝物,CDもしくは類似の電子媒体のラベルなどの印刷物における利用,(2) 学会および出版社のホームページ,論文データベース等,Fisheries Science誌に関するインターネットサイトにおける利用,(3) 学会の活動報告資料における利用について,学会が採用作品を独占的に利用することを了承していただきます。採用作品の利用期間は,採用作品が表紙として使われる平成26年12月末日までとしますが,それまでに製作した表紙デザインの複製物および翻案は,継続的に学会が利用できることとします。以上の範囲以外で学会が採用作品を利用する場合は,事前に応募者との間でその条件について協議するものとします。 |
編集委員会委員長 松永茂樹Fisheries Science 79巻表紙写真などの募集について
このたび,来年の79巻の表紙に掲載する6枚の写真・図を日本水産学会会員の皆様から募集いたします。写真は漁業,養殖,水産生物,水産食品など水産学会が扱う範疇であれば特に制限するものはありませんが,一枚の写真でインパクトのある内容を表現できることが要求されます。また,日本水産学会誌,Fisheries Scienceに掲載された図や写真などでもかまいません。写真の画像は,必ず300 dpi以上のTIFFかEPSファイルとしてください。内容がわかる簡単な英語の説明とともに,日本水産学会編集のe-mailアドレスfsjpubl@d1.dion.ne.jp宛に添付ファイルで応募頂くか,CD等のディスクにコピーしたものを郵送してください。締め切り日は6月末日とし,7月に開催する編集委員会で選定いたします。掲載が決定した方には,Fisheries Science 79巻を6冊(1〜6号各1冊)進呈致しますので,奮ってご応募ください。なお,掲載された図の著作権は日本水産学会に帰属させて頂きます。過去に発行されましたFisheries Scienceの表紙デザインは,学会ホームページ http://www.office.jsfs.jp/fs-cover2.htmlでご覧いただけます。
編集委員会委員長 松永茂樹日本水産学会誌J-STAGEオンライン公開ページのシステム変更について
全体的に,見やすく,使い勝手のよいデザインとなりました。また,J-STAGE @rchiveがなくなり,創刊号から最新号まで同じサイトからアクセスできるようになったほか,便利な機能がたくさん付きました。本サイトを有効にお使いくださいますようご案内いたします。
なお,Fisheries Scienceについては,J-STAGE@rchiveで公開していた60巻から70巻が新サイトhttps://www.jstage.jst.go.jp/browse/fishsci1994/-char/ja/に移行しますが,71巻以降の新しい巻号は引き続きSpringerLink(http://www.springerlink.com/content/0919-9268)にてご覧ください。
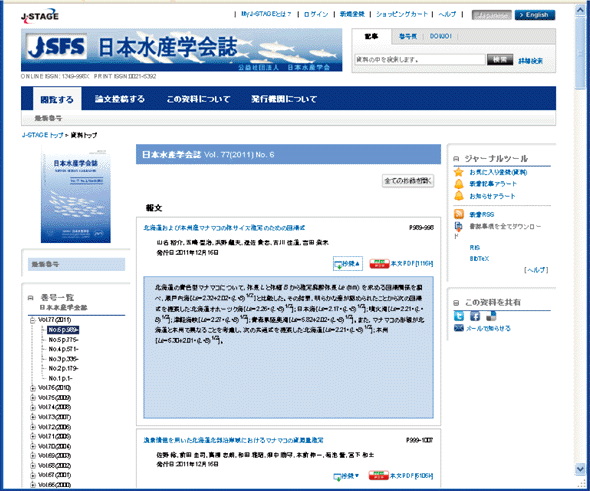
編集委員会委員長 松永茂樹
J-STAGEにおける日本水産学会誌の電子ファイル閲覧のフリー化について
| ・ | Copyright Transfer Statement(著作権移譲書)の提出 |
| ・ | 別刷(Offprint)の注文 |
| ・ | カラー印刷の注文 |
これに伴い,別刷代金とカラー印刷費用は,論文掲載料とは別の請求となります。別刷代金とカラー印刷費用についてはシュプリンガー社に,論文掲載料は日本水産学会にお支払いいただくことになります。
MyPublicationの利用は,原稿の受理確定後にシュプリンガー社から届くメールに従ってMyPublicationにアクセスし,その記載にしたがってお手続きください。そのほか,MyPublicationを利用する著者として受けられる特典,例えばシュプリンガー社刊行の書籍の割引購入等の詳細は,MyPublicationアクセス時にご覧ください。
編集委員会委員長 松永茂樹
編集委員会委員長 松永茂樹
なお,Fisheries Science の投稿審査システムについては変更ありません.
編集委員会委員長 松永茂樹
このたび,来年の 78 巻の表紙に掲載する6枚の写真・図を日本水産学会会員の皆様から募集いたします。写真は漁業,養殖,水産生物,水産食品など水産学会が扱う範疇であれば特に制限するものはありませんが,一枚の写真でインパクトのある内容を表現できることが要求されます。また,日本水産学会誌,Fisheries Science に掲載された図や写真などでもかまいません。写真の画像は,必ず 300 dpi 以上の TIFF か EPS ファイルとしてください。内容がわかる簡単な英語の説明とともに,日本水産学会編集の e-mail アドレス fsjpubl@d1.dion.ne.jp 宛に添付ファイルで応募頂くか,CD等のディスクにコピーしたものを郵送してください。締め切り日は 6月末日 とし,7 月に開催する編集委員会で選定いたします。掲載が決定した方には,Fisheries Science 78 巻を 6 冊(1〜6号各1冊)進呈致しますので,奮ってご応募ください。なお,掲載された図の著作権は日本水産学会に帰属させて頂きます。
編集委員会委員長 竹内俊郎
9月の会告でご案内しましたように、Fisheries Science誌はOnline Firstを導入し、より早い公開をめざして準備を進めてまいりましたが、平成20年12月18日より、シュプリンガー社の電子ジャーナルサイトhttp://www.springer.com/12562にて、公開が開始されましたのでお知らせいたします。
J-STAGEにおける日本水産学会誌の
電子ファイル閲覧のフリー化について日本水産学会誌における投稿審査システムの移行について
Fisheries Science 78 巻表紙写真などの募集について
Fisheries Science 誌のOnline First 公開のお知らせ
当初はフリーアクセスとなっており、上記サイトにて、無料でどなたでもご覧になれます。後日、会員の皆様には、認証のご案内をいたします。
Online Firstでは、受理された論文ごとにシステムに入稿後、最終版が約6週間で正式にオンライン出版されます。オンライン出版日(DOI)が明記されますので、引用が可能です。冊子はその後、2カ月に1度まとめて印刷されます。
改訂されたINSTRUCTIONSがhttp://www.miyagi.kopas.co.jp/JSFS/bosyuu.htmlに載っておりますので、よろしくお願いいたします。日本水産学会誌の「原稿の書き方」とは一部異なりますのでご注意ください。
| 1) | 今後、電子投稿査読システム(web投稿)が実施されると、査読の際にAbstractが必要になり、短報にも付ける必要が生じ、2ページで収めるのはかなり困難となる |
| 2) | 現在、短報を発行する意味があまりない(データ不足や、内容が少ない原稿を短報でという方向性が強い) |
| 3) | インパクトファクターを上昇させるためには短報はないほうがよい |
短報をお考えの著者にはまことに申し訳ありませんが、今回の変更に対しましてご理解のほど、お願い申し上げます。
なお、これまでの短報には速報性を期待するところもありました。そこで編集委員会では、新たに「速報」を設ける方向で検討を進めております。今後、決定した折には再度ご連絡いたします。
Journal@rchiveのFISHERIES SCIENCEのページ(http://www.journalarchive.jst.go.jp/japanese/jnltop_ja.php?cdjournal=fishsci1994)をご覧ください。
FISHERIES SCIENCEVol.66〜最新号までの電子ジャーナルはこれまでどおりWiley InterScienceをご利用ください。Wiley InterScienceは初回のみ利用登録が必要です。登録方法はコチラをご覧ください。
投稿用電子ファイル原稿の提出要領FISHERIES SCIENCEのアーカイブについて
FISHERIES SCIENCE Vol.60(1994)〜Vol.65(1999)およびVol.68 Supplement1&2
このたびJournal@rchiveでFISHERIES SCIENCE Vol.60〜65およびVol.68のSupplement1&2の電子ジャーナルが収録・公開されました。今後,Vol.70まで収録・公開の予定です。
なお,日英混載だったVol. 59 (1993) まではJournal@rchiveの日本水産学会誌のページ(http://www.journalarchive.jst.go.jp/japanese/jnltop_ja.php?cdjournal=suisan1932)に掲載されております。
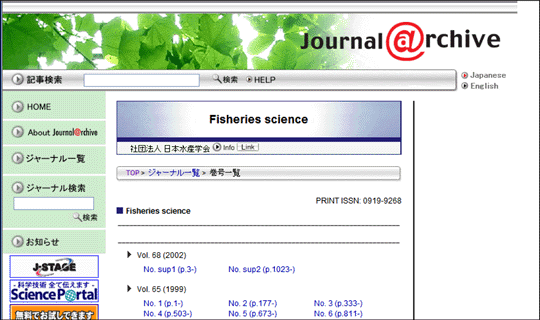
「Fisheries Science」の電子ファイル(PDF)原稿による投稿について
日本水産学会では「Fisheries Science」への投稿原稿について,校閲および審査等の編集作業の迅速化を図るために電子ファイル(PDF)による投稿を試行的に受け付けております。つきましたは,原稿を投稿される際には下記の要領をご確認下さい。
なお,「日本水産学会誌」につきましては,Web投稿でお願いいたします。
| ・ | 投稿原稿のファイル形式はPDFに限ります。(送付された電子ファイルは校閲・審査作業のみに使用し,日本水産学会のプライバシーポリシーに基づいて取り扱われます。) |
| ・ | 電子ファイルは図表も含めて可能な限り1つのファイルにまとめ,1Mb程度の容量でディスク(FD,CD等)に保存すること。カラー写真等でファイルサイズが大きい場合は解像度を落として保存すること。 |
| ・ | 電子ファイル原稿は印刷原稿と同様に投稿規程,原稿の書き方に従って作成する。電子ファイル原稿のスタイルは印刷原稿と一致していること。 |
| ・ | 電子ファイルのディスク1枚,投稿カード,印刷原稿1部を次の住所に送付する。電子ファイルをメールで送付しない。 |
〒108-8477 東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学内 日本水産学会事務局
Fisheries Science の原著論文の分析―インパクトファクター向上を目指して―
編集委員 渡邊良朗(東大海洋研)・渡部終五(東大院農)
1. は じ め に
日本水産学会の国際誌 Fisheries Science(以下 FS)が 1994 年に日本水産学会誌から独立して 8 年が経過した。Blackwell Science Asia 社の 2000 年の年報によると,Institute for Scientific Information (ISI) による FS の 1999 年のインパクトファクターは 0.542 で(2000 年は 0.459, 2001 年は 0.593),ISI に登録されている水産学分野の国際誌 34 誌のうち 25 位の位置にある。インパクトファクターは,ある学術誌に掲載された論文の被引用頻度によって,その学術誌の当該研究分野に対する影響力の大きさを示す指標であり,今日一般的に用いられる学術誌の評価指標である。FS の 1999 年のインパクトファクターは,1999 年に出版された ISI に登録されている学術誌中の論文に引用された,前 2 年(1997, 1998 年)の FS 掲載原著論文(Original article と Short paper)の被引用回数を,1997, 1998 年に出版された FS 誌の総原著論文数で除した値として表される。
日本水産学会編集委員会では,FS のインパクトファクターを 1.0 前後に高めることを当面の目標と考えている。この目標を達成するための戦略を具体化するために,1994 年以降に FS に掲載された Original article と Short paper について,被引用回数を調べた。一般に,論文はその論文が掲載された雑誌において最も頻度高く引用される。したがって,FS の原著論文の引用文献数は FS のインパクトファクターを左右すると考えられるので,各原著論文の引用文献数についても調べた。これらの結果に基づいて,FS のインパクトファクターを高めるための編集方策について検討した。
2. 対象年と調査方法
1994〜1999 年の 6 年間に出版された FS 60〜65 巻(合計 36 号)に掲載された Original article 980 編と Short paper 270 編を調査の対象とした。2000 年以降の論文については,出版からの経過時間が短いので,調査対象から除外した。
6 年間に出版されたすべての原著論文について,2002 年 1 月末に学術論文データベース Web of Science によって,論文個々に総ページ数,引用文献数,被引用回数を調べた。また,個々の論文の第 1 著者の所属を,大学,水産庁研究所,都道府県水産試験試験場等,その他の機関,の 4 つに分類した。これらのデータを,Original article と Short paper という 2 つの原著論文カテゴリーで比較検討した。
3. 結 果
1994〜1999 年に年間 137〜185 編の Original article が掲載され(表 1),6 年間の総 Original article 数は 980 編であった。Original article 1 編あたりのページ数は 1994 年に 4.8 であったが,この 6 年間でやや増加傾向にあり,1999 年には 5.9 ページとなった。3 ページ以下の Original article が 72 編と全体の 7.3% を占めた。
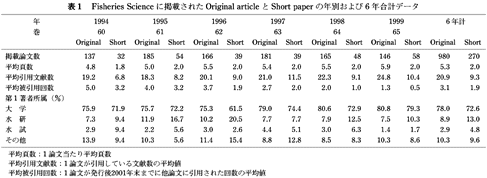
1994〜1999 年の Short paper 数は年間 32〜58 編で(表 1),6 年間の総数は 270 編であった。Short paper は刷り上がりページ数に制限があることから,1 編あたりページ数は約 2.0 でほぼ一定していた。
Original article 1 編あたり引用文献数の年平均値は 18〜25 であった。6 年間の Original article の引用文献数は 0〜63 の範囲にあって,図 1 のように 17 を最頻値とする単峰形の頻度分布を示し,平均 20.9±9.3 であった。980 編の Original article のうち,引用文献 0 の Original article が 1 編あり,5 以下が 7 編,10 以下の引用文献数の Original article が 103 編(10.5%)あった。
Short paper 1 編あたりの平均引用文献数は,1994 年の 6.8 から増加傾向にあり,1999 年では 10.4 であった。6 年間に出版された 270 編の Short paper の引用文献数は 1〜30 の範囲にあり,図 1 のように 6 と 7 を最頻値とする単峰型の頻度分布を示した。6 年間の Short paper 1 編あたり平均引用文献数は 9.3±4.9 であった。引用文献数 5 以下の Short paper が 47 編と全体の 17% を占めた。
Original article 1 編あたりの平均被引用回数は,当然のことながら出版後の経過年数が多いほど多く,1994 年は 5.0±5.0, 1999 年には 1.3±1.4 回であった(表 1)。6 年間の 980 編について被引用回数の頻度分布を見ると,被引用回数 0 回(197 編)と 1 回(203 編)を最頻値として指数関数的に減少する分布型を示し(図 2),6 年間の平均値と標準偏差は 3.1±3.6 であった。
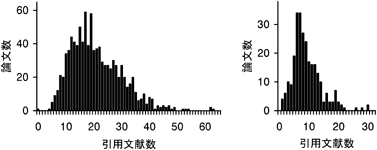
図 1 Original article(左)と Short paper(右)の引用文献数頻度分布
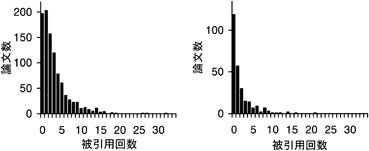
図 2 Original article(左)と Short paper(右)の被引用回数の頻度分布
Short paper 1 編あたりの平均被引用回数は,1994 年で 3.2±4.1, 1999 年では 0.5±1.1 であった(表 1)。6 年間に出版された 270 編の Short paper について被引用回数の頻度分布を見ると,0 回の 119 編を最高に指数関数的に急激に減少する分布型を示し(図 2),6 年間の平均値は 1.9±3.0 回であった。
各年に出版された Original article の第 1 著者の 75〜80% は大学に所属しており,6 年間の 980 編の 78.0% を占めた。水産庁研究所の研究者は各年で 7〜12%, 6 年間の総計の 8.9% を占め,都道府県水産試験場等の研究者は年 1〜4% で,6 年間の総計では 2.9% であった(表 1)。
Short paper の第 1 著者の所属機関構成を年ごとに見ると 60〜80% が大学であり,6 年間に出版された 270 編の 72.6% を占めた(表 2)。水産庁研究所の研究員を第 1 著者とする Short paper の割合は 7〜21% の範囲にあり,6 年間の総計で 13.0% であった。都道府県水産試験場等の割合は 10% 以下で,6 年間の総計では 4.8% であった。
6 年計について,第 1 著者の所属別に総原著論文数に占める Short paper の割合を計算すると,大学 23.4%,水産庁研究所 28.7%,都道府県水産試験場等 31.7%,その他の機関 20.6% となった。
1999 年 2〜12 月に出版された原著論文は,2002 年 1 月の調査時点で,出版後 2 年 1 月〜2 年 11 月を経過しているので,1999 年出版の 204 編を出版後 2 年経過とした。1998 年に出版された原著論文を同様にして出版後 3 年経過,1997 年を 4 年経過とし,1 編あたり平均被引用回数の経過年数に伴う変化を調べた。
Original article および Short paper のいずれも出版後の経過年数の増加にしたがって,1 編あたり被引用回数は直線的に増加した(図 3)。Original article と Short paper を比較すると,出版後 2 年で被引用回数に有意な差があった(Mann-Whitney U-test, P<0.001)。Original article の回帰直線の傾きは 0.72 と Short paper の傾き 0.57 より大きいため,平均被引用回数の差は経過年数の増加とともに大きくなり,7 年後には Original article 5.0±5.0 に対して Short paper 3.2±4.1 となった。
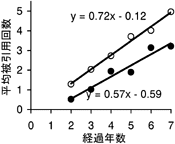
図 3 Original article(○)と Short paper(●)の被引用回数の出版後経過年数に伴う変化
4. 論 議
この報告は FS に掲載された原著論文(Original article と Short paper)についての全数調査の結果であり,Short paper の被引用回数は表 1 の数字に現れた通りに Original article より少ないということになる。表 1 の被引用回数は出版から 2002 年初めの調査時点までの累積値であり,この表からインパクトファクターを求めることはできない。しかし,調査した 6 年間のうちの最近年である 1998 年と 1999 年についてみると,Short paper 1 編あたり被引用回数は Original article の約半分であること,Short paper 数は全原著論文数の 23% を占めていることから,出版後 1〜2 年の被引用回数から求められるインパクトファクターを 0.1 程度引き下げる結果となっていたと推測される。現在 FS の Short paper 掲載数は各号 5 編,年間 30 編以下に抑えられており,そのために受理から掲載まで 1 年以上を要している。このように掲載数を全原著論文数の十数%に制限してもなお,Short paper は FS のインパクトファクターを 10% 程度引き下げる結果となると判断される。
Short paper の存在理由として,都道府県水産試験場等や水産庁研究所の研究員にとって投稿しやすいということが想定された。Short paper の第 1 著者の所属機関構成を年ごとに見ると,水産庁研究所や都道府県水産試験場等において,Original article より Short paper における構成比率が高かった。第 1 著者の所属別に 6 年間の総原著論文数に占める Short paper の割合を見ると,大学<水産庁研究所<都道府県水産試験場等となり,Short paper は都道府県水産試験場等や水産庁研究所の研究員によってより多く利用されていた。このような Short paper の利用状況をふまえて,Short paper を設けることの意義を,FS のインパクトファクターを高めるという編集方針の中で再吟味する必要がある。
原著論文 1 編あたりの引用文献数は Short paper で平均 9, Original article で平均 21 であった。研究分野によって原著論文 1 編あたりの引用文献数の平均値は異なると考えられるが,ISI のインパクトファクター上位にランクされる水産学分野の原著論文学術誌 Fisheries Oceanography や Canadian Journal of Aquatic and Fisheries Sciences と比較すると,FS の平均引用文献数は少ないと思われる。すでに述べたように,一般に,論文はその論文が掲載された雑誌において最も頻度高く引用されることを考えると,引用文献数の少なさは,FS のインパクトファクターを抑える要因となっていると判断される。
5. 結 論
Short paper がインパクトファクターを下げる要因となっていることが明らかになったので,Short paper の掲載数を少なくすることが,FS のインパクトファクターを引き上げるための編集方針の第 1 と考えられる。
第 2 の編集方策として,各報文の Introduction や Discussion を充実させて,報文内容に関連する文献が広く引用されるように編集過程で著者に指示することが考えられる。FS の原著論文が FS の原著論文中で多く引用されると,FS のインパクトファクターは高くなる。
Short paper 掲載数をどの程度に抑えるかについては,都道府県水産試験場等や水産庁研究所の研究員にとっての利用価値とインパクトファクターへの影響とを考慮して判断する必要がある。
本報告をとりまとめるに当たり,会田勝美編集委員長はじめ編集委員各氏から貴重なご意見をいただいたことに感謝する。本報告の基礎データは,東大海洋研究所資源生態分野の渡部諭史(現中央水産研究所),山口素臣(海洋科学特定研究員),杢 雅利(学振特別研究員)の 3 氏によって作成された。
日本水産学会論文賞の新設について
編集委員長 会田勝美
平成14年9月に開催された(社)日本水産学会第3回理事会において、学会誌のさらなる充実を目指して、論文賞を新設することが承認されましたので、お知らせいたします。選考の対象となる論文は、Fisheries Science誌および日本水産学会誌に掲載された原著論文(総説と短報を除く)です。毎年1〜6号に掲載された論文のなかから、数編の優れた論文が論文賞選考委員会(編集委員会)で選ばれ、翌年の総会で表彰されます。第1回の選考は、2003年69巻1〜6号に掲載される論文が対象となりますので、奮ってご投稿ください。